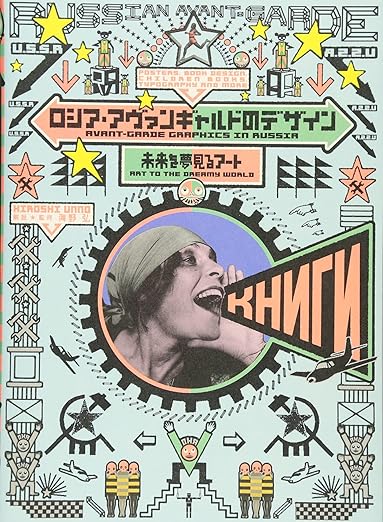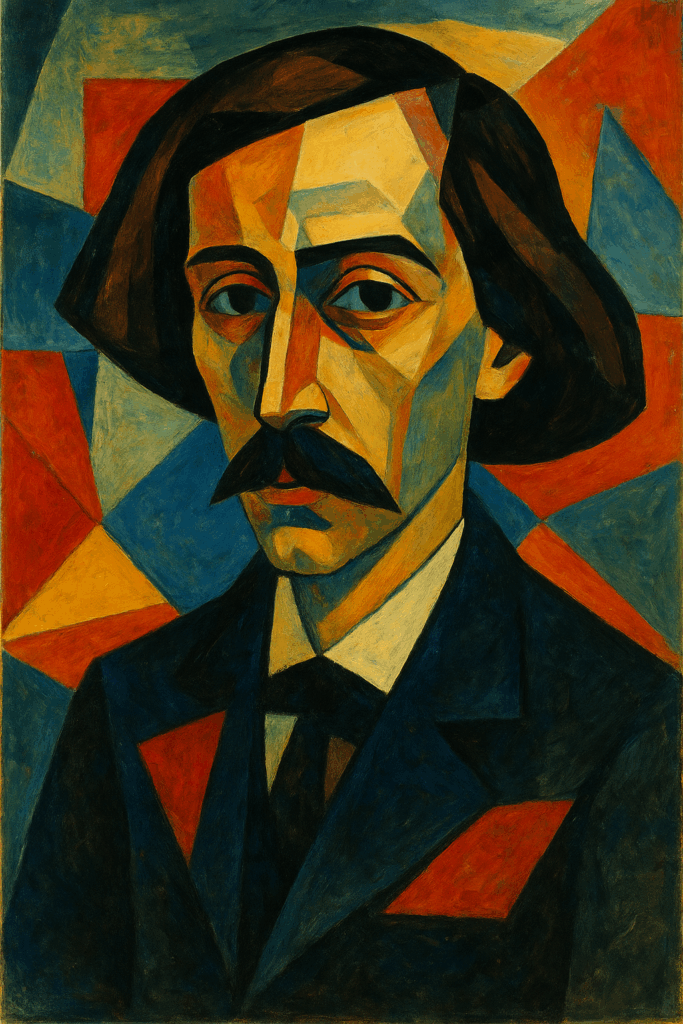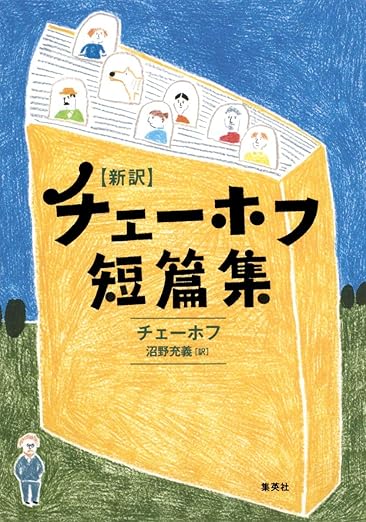ロシア語の学習で避けて通れないのが 運動の動詞(глаголы движения) です。日本語や英語の「行く」「来る」に比べて種類が多く、方向性や手段によって細かく区別されます。ここでは体系的に整理し、学習の助けとなる一覧表を示します。
1. 運動の動詞の二つのタイプ
ロシア語の運動動詞には 一方向性(однонаправленные) と 無方向性(многонаправленные) の対立があります。
- 一方向性 … 「今、ある特定の方向へ進んでいる」
- 無方向性 … 「あちこち行く」「繰り返す」「習慣」
例:
- идти(徒歩・一方向) ↔ ходить(徒歩・無方向)
- ехать(乗り物・一方向) ↔ ездить(乗り物・無方向)
2. 移動手段ごとの主要動詞一覧
| 手段 | 無方向性(習慣・往復) | 一方向性(現在進行・一度の移動) |
|---|---|---|
| 徒歩 | ходить | идти |
| 乗り物 | ездить | ехать |
| 飛行 | летать | лететь |
| 水上 | плавать | плыть |
| 走る | бегать | бежать |
| 這う | ползать | ползти |
| 登る | лазить | лезть |
| 運ぶ | носить | нести |
| 乗せる(運転) | возить | везти |
| 追う | гонять | гнать |
3. 用法の対照表
| 例文 | 意味 | 解説 |
|---|---|---|
| Я иду в школу. | 私はいま学校へ歩いて行っている。 | идти(徒歩・一方向、進行中) |
| Я хожу в школу каждый день. | 私は毎日学校へ通っている。 | ходить(徒歩・無方向、習慣) |
| Он едет в Москву. | 彼はモスクワへ向かっている(乗り物)。 | ехать(一方向) |
| Он часто ездит в Москву. | 彼はよくモスクワへ行く。 | ездить(無方向、習慣) |
| Самолёт летит в Токио. | 飛行機が東京に向かっている。 | лететь(一方向) |
| Птицы летают над морем. | 鳥たちが海の上を飛んでいる。 | летать(無方向、繰り返し) |
4. 完了体との関係
運動の動詞は基本的に不完了体ですが、目的地到達を表すときには完了体が用いられます。
- прийти(徒歩で到着する)
- поехать(乗り物で出発する)
- прилететь(飛行機で到着する)
👉 不完了体:動作の過程(「行っている」「通っている」)
👉 完了体:動作の結果(「到着した」「出発した」)
5. 学習のポイント
- идти / ходить、ехать / ездить の4つをマスターする。
- 次に лететь / летать、плыть / плавать を覚える。
- 習慣と一回限りの移動を意識して文を作る。
- 完了体を合わせて使い分けられるようにする。
まとめ
ロシア語の運動の動詞は、「方向」「習慣性」「移動手段」という3つの要素で意味が変わります。最初は複雑に感じますが、一覧表と対照表を参考に練習すると理解が深まります。マスターすれば、ロシア語での表現力が格段に広がります。