ニコライ・ヴァシーリエヴィチ・ゴーゴリ(Николай Васильевич Гоголь, 1809–1852)は、19世紀ロシア文学において決定的な役割を果たした作家です。彼の作品は、幻想的で怪奇なイメージと、鋭い社会風刺、そして深い人間存在への洞察が結びつき、後世の文学に巨大な影響を与えました。ドストエフスキーは「私たちは皆、ゴーゴリの『外套』から出てきた」と語ったと伝えられていますが、この言葉は彼の文学的遺産の大きさを端的に示しています。
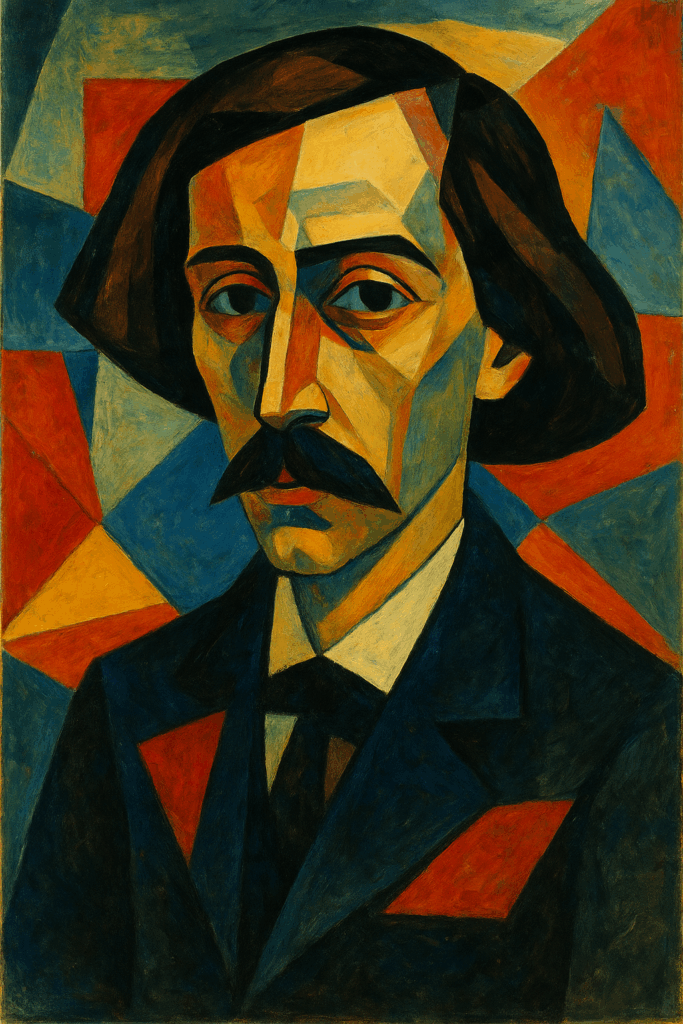
生涯と背景
ゴーゴリは1809年、現在のウクライナ・ポルタヴァ地方のソロチンツィ村に生まれました。父は地方貴族で、民話や芝居を愛していたことから、幼い頃からウクライナの伝説や口承文化に親しみました。この豊かな民俗的背景は、後年の幻想的な短編に色濃く反映されます。
若くしてペテルブルクに出たゴーゴリは、官僚として職に就きますが、退屈で形式主義に満ちた官僚生活に強い違和感を覚えます。そうした経験は、のちに『鼻』や『外套』といったペテルブルクを舞台にした風刺的作品の素材となりました。1830年代、彼はプーシキンと出会い、その助言と励ましを受けて本格的に作家としての活動を始めます。この出会いが、ゴーゴリをロシア文学の中心へと導いたのです。
主な作品とその特徴
- 『ディカーニカ近郊の夜』(1831–32)
初期の短編小説集で、ウクライナの伝説や民話をもとにした作品群。奇怪でユーモラスな人物像が登場し、ゴーゴリの独自の文体と想像力が初めて鮮やかに示されました。 - 『鼻』(1836)
官僚コワリョフの鼻が突然消え、しかも独立した人格を持って街を歩き出すという不条理な物語。荒唐無稽でありながら、人間のアイデンティティや社会的地位に対する痛烈な風刺が込められています。 - 『外套』(1842)
貧しい下級官吏アカーキイ・アカーキエヴィチが、新しい外套を手に入れることで一瞬の幸福を味わうも、やがて不条理な運命に翻弄される物語。弱者の悲哀と社会の冷酷さが象徴的に描かれ、ロシア文学の転換点となりました。
- 『死せる魂』(第一部 1842)
主人公チチコフが農奴台帳上の「死んだ農奴」を買い集めるという奇妙な計画を進める物語。表面的には詐欺譚ですが、その背後には農奴制社会の腐敗と空虚、そしてロシア的精神の追求が描かれています。未完のまま終わりましたが、ロシア文学史における最大級の傑作とされています。
文学的特徴
ゴーゴリの文体は、常に笑いと恐怖の二重性を持ち合わせています。彼の描くユーモアは単なる娯楽ではなく、人間の愚かさや社会の矛盾を浮き彫りにする手段でした。一方で、その笑いの裏には不気味な不安感や存在的虚無が潜んでいます。
また、ゴーゴリは都市ペテルブルクを舞台とする作品を通して、近代都市における人間疎外やアイデンティティの喪失を鮮烈に描きました。その視点は後のカフカやモダニズム文学へとつながる先駆的なものでした。
晩年と宗教的葛藤
1840年代後半、ゴーゴリは精神的な危機に直面します。宗教的な救済への渇望に駆られ、苦悩しながら『死せる魂』第二部を執筆しますが、その原稿の多くを自らの手で焼き払ってしまいました。これは彼の内面的な葛藤の象徴ともいえる出来事であり、芸術と信仰、世俗と神聖の間で引き裂かれた作家の姿を物語っています。
1852年、モスクワで病に倒れ、42歳という若さでこの世を去りました。短い生涯ながらも、その文学的遺産は時代を超えて生き続けています。
影響と評価
ゴーゴリの影響は計り知れません。ドストエフスキーやトルストイといったロシアの大作家はもちろん、20世紀のカフカ、さらには現代の不条理文学や演劇にまでその痕跡が見られます。彼の作品に漂う奇怪な笑いと不安は、時代や国境を超えて普遍的な力を持ち続けています。
ゴーゴリは単なる風刺作家ではなく、ロシア文学の根幹に幻想と不条理の要素を組み込み、人間存在の滑稽さと悲劇性を同時に描き出した先駆者でした。その作品は今なお新鮮な問いを投げかけ、私たちを不思議な魅力の世界へ誘い続けています。



